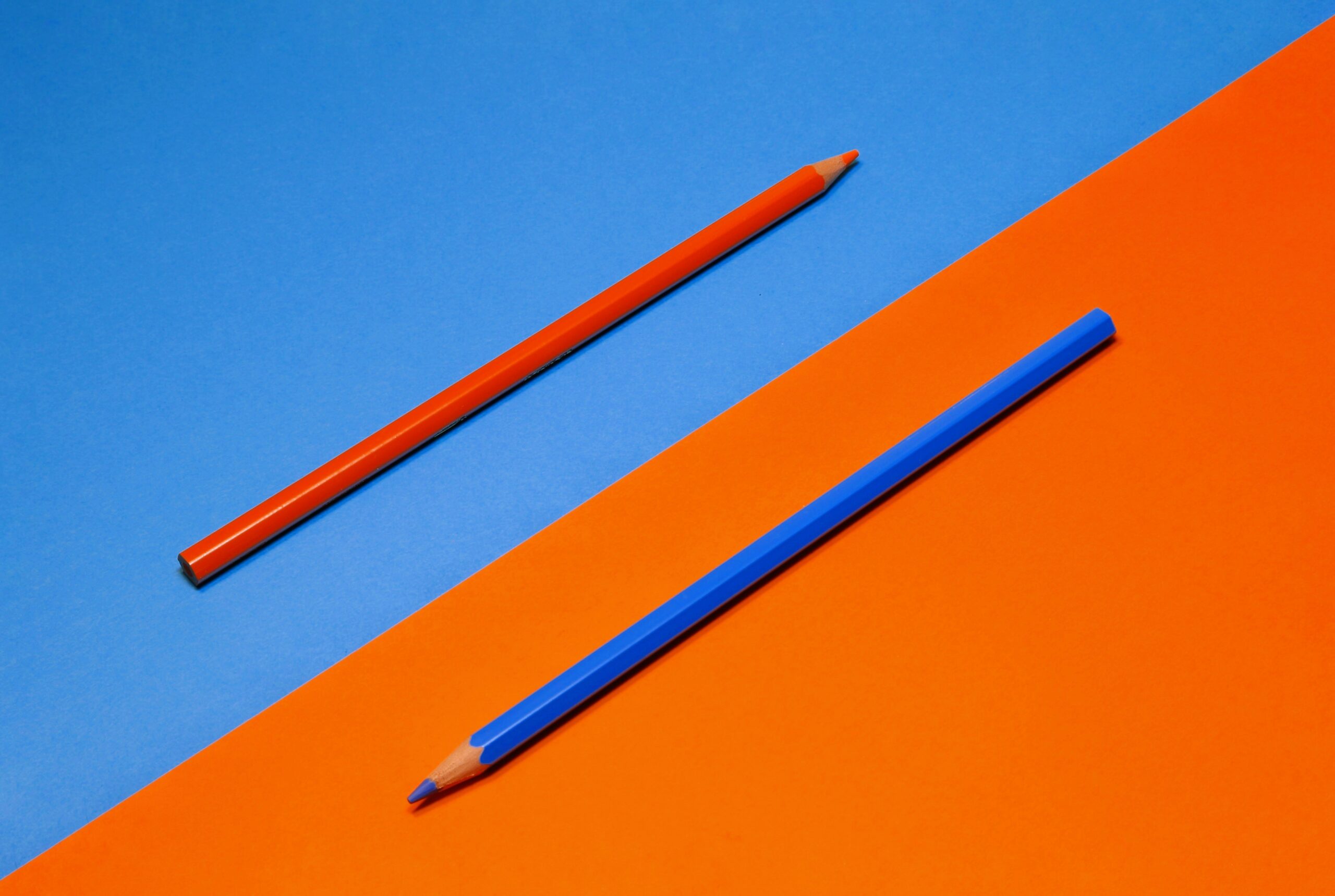「ちょっと手持ちないから、借りるよ。」
夫が家計用財布から1万円札を抜いたのが先月のこと。
まだ返して貰ってない。
2度程、返してと頼んだのだが、のらりくらりかわされ今日に至る。
一応、予備費としていくらか別に置いているので何とかなっているけれど、コルセンパート代が来月は殆ど入らないので、こんな風に毎回抜かれたらやり繰りが困る。
家計簿を一週間ぶりにつけた。
おかしい。
1万ちょっと足りない。
家計用財布は基本私が持ち歩いているのだけれど、時々夫婦共有のチェストの引き出しに入れていることもあり、夫がちょっと買い物に行く時などはそこから出して使っている。
だが、レシートもないのでこの不足分の理由が分からない。
数百円なら自分の虎の子から補填するけれど、さすがに1万は多い。
なので、夫に聞いてみた。
「お金が合わないんだけど、覚えある?」
「いや・・知らん。」
だが、先週ガソリンを入れに行くとかなんとかで財布を持っていたような気もしたので聞いてみた。
「あー、そうだったかもな。じゃあそういうことで。」
夫が家計を管理していた時は、私の買い物についていちいちレシートを細かくチェックしていた癖に、同じ人間とは思えないずぼらさ。
そもそも、私がパートをするようになりなあなあになっている現実。やりくり費の半分は私が出すーしかも予算オーバーならそれもパート代からという決まりになってからだから、釈然としない。
「来月から、半分は出せないかも。」
「え?じゃあ、それはつけといて。新しいパート先が決まったらその分後付けで。」
有無を言わせず。
家賃や光熱費などの固定費は俺が払ってるんだからそれくらいーそんな顔をする。
子が義父から貰った学費を使い込んだことは忘れているのか。
夫が信用出来ないから、わずかでも私のパート代から子の為に貯金したいのに。
それを伝えると機嫌が悪くなる。
「あなたさ、ここ数年パートごときで働いただけで勘違いしてない?もっと家に入れてる主婦はいるよ。」
こちらの分が悪くなるので、強く言えない。
夫婦間の生活費負担割合ー、共働きならきっと半々。家だってペアローンの時代。
専業主婦を養う昭和モデルの夫婦の形は今や希少。
食費はパート代からーなんて家庭は星の数程いる現状。
パターンは家庭によりいくつかあって、
①全額を一方が負担→これは、私が専業主婦時代のやり方で、夫も会社員で収入も安定していたので家計のすべてを担ってくれていた。代わりに、夫がすべてを管理するという条件の元。家にどれだけの資産があるかも分からず、また数万円のやり繰り費のみでなんとかしなくてはならず、更にレシートチェックや不足分の申し立てには精神的苦痛を伴うことも多かった。
②一定額を共通口座に入金→これはやり繰り費を互いの稼ぎからいくら出すと決めて残りは互いに干渉せず自由に使うというパターン。これは曖昧な部分も多く、互いに果たしてどれだけ貯金しているのかわ分からない。子どもがいない夫婦に多いらしいやり方。
自分の老後資金は自己責任でという感じ。
また、収入に応じての割合となっていることが多く、正社員ではないパート主婦であってもこのパターンを採用している家庭は割と多いらしい。
③項目別に負担→家賃や光熱費などは夫、食費や子ども費は妻ーという項目別での負担割合。
我が家は、やり繰り費の中に食費や子ども費や雑費があるのだけれど、それの半分をパート代から出すというルールなので、ややこのパターン寄りかなと思う。
④夫婦の収入をまとめてそれぞれ小遣い制→一番理想的なパターン。収入も支出も透明化されるし、何より平等な気がする。夫が今自営でどれだけの稼ぎがあってーいや赤字なのだとしたらどれだけ蓄えがあって、何をどう使っているのか。やりくり費の中だけでは分からない部分が重要なのだ。
固定費も、家賃や光熱費の出費は何となく分かるけれど、それ以外ー車やバイクの維持費だったり交際費が良く分からない現状。
それがクリアになれば、少なくとも今より将来の見通しが立つ気がする。
結局のところ、ここでウダウダ言っているところで何も変わらない。
面と向かって夫に言えない、それが諸悪の根源。
言えない理由はずばり、私自身の問題。私が夫に対し罪悪感を抱えているから。
所詮、養ってもらっているという弱さがどうしたって先に立つのだ。
子には、自分の食い扶持は勿論のこと、やはり経済的にも精神的にも自立して欲しい。
結婚したとして、夫婦対等であって欲しい。
だから、大学進学は取り敢えずの絶対条件なのだ。